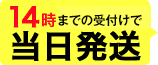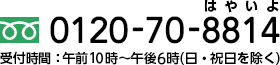はじめに
カメラの世界はとても深い。
最近のデジタルカメラはシャッターを押せば、誰でも簡単にいい感じの写真を撮ることができます。
しかし、簡単に写真を撮る事ができる一方で、カメラのしくみを知らないまま”なんとなく”で撮っている人も増えているように感じます。
例えば、撮影した写真を見て「思ったイメージとは違うな…」と感じた事はありませんか?
イメージと違う写真になった原因は様々あるので一概には言えませんがカメラについて知っていけば、イメージ通りの写真を撮るハードルが低くなってきます。
カメラの機能はたくさんありますが、今回は私が初心者を脱出できた!と感じた露出についてや露出補正を使う場面について紹介していきます。
露出とは
露出とは「シャッタースピード」「絞り」「ISO感度」の組み合わせにより決まるレンズに取り込まれる光の量のことをいい、それぞれ数値の上げ下げで露出がプラスまたはマイナスになり、写真を暗くしたり、明るくしたりすることが出来ます。
それでは、それぞれの設定で、露出を構成している、シャッタースピード・絞り・ISO感度について掘り下げて説明していきます。
(1)シャッタースピードについて
シャッタースピードとはいわゆるシャッターが開いている時間です。
カメラの構造として、レンズとイメージセンサー(撮像素子)の間にシャッターがあります。イメージセンサーとは、レンズから入った光を受け取り、その光を電気信号に変換し、データ転送する役割の半導体です。
シャッターボタンを押すとシャッターが開き、決められたシャッタースピードに応じて閉じて行きます。
シャッタースピードによりイメージセンサーが受け取れる光の量が変わる、つまり写真の明るさ、暗さに影響するということですね。
シャッタースピードを遅くするとカメラの中に光を取り込む時間が長くなるので、明るい写真となります。反対にシャッタースピードを速くすると、カメラの中に光を取り込む時間が短くなり、暗い写真になります。
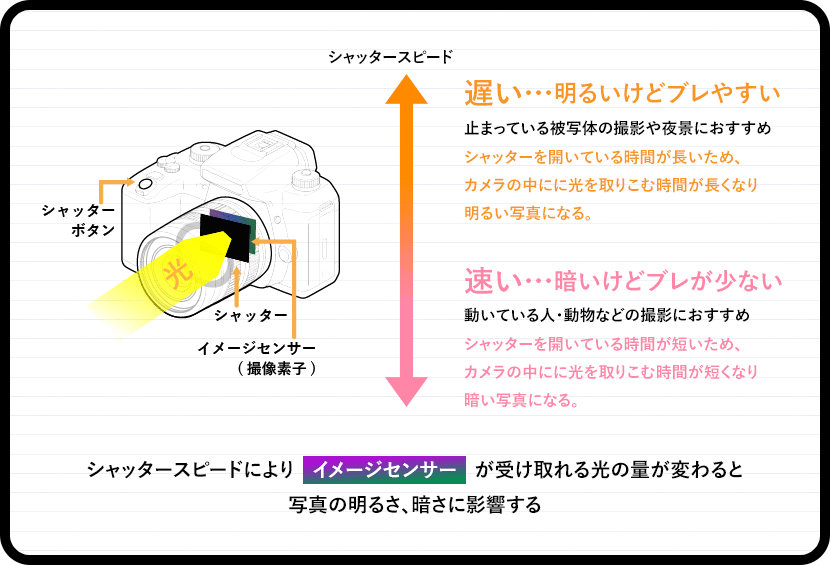

シャッタースピードの遅い写真は長い時間を切り抜いた空間を撮影できます。光の量を多く取り込めるので夜景の撮影などに向いています。
シャッタースピードの速い写真は光の取り込む量が少なくなりますが、動きの速い被写体の一瞬をとらえることができます。屋外のスポーツの撮影や動きの速い動物を撮るときなどに向いています。
ただしシャッタースピードが遅いと言うことはシャッターが開いている間(イメージセンサーに光が当たり続ける間)にカメラが動いてしまうと、「手ブレ」が発生してしまいます。カメラが動くと手ブレになり、被写体が動くと被写体ブレが生じることがあります。
手ブレが気になるときは?
手ブレが気になる場合、三脚を使うなどカメラが固定されるように工夫しましょう。ほかシャッタースピードを速くすると良いですが暗い場所は明るさが足らなくなります。その場合はストロボなどで光源を増やすなどの対策をしましょう!
他、後述していますが絞りや露出の調整で明るくする方法もあります。
(2)絞り(F値)について
絞り(F値)とはカメラのレンズから入ってくる光の量を穴(絞り羽根)で調整することです。
絞り(F値)の数値を小さくすれば小さくするほど絞り羽根が開放され(開かれ)、光の量は増加、写真が明るくなります。
逆に絞り(F値)の数値が大きければ大きいほどレンズ内の絞り羽根が絞られ(閉じ)ていき光の量は減少、写真が暗くなります。

また、絞り(F値)を小さくして、絞り羽根を開放すると、被写界深度が浅い写真となりピントが合う部分が狭くなり、ピントが合っていない部分はボケていきます。
逆に、絞り(F値)を大きくすると、被写界深度が深い写真となり広い範囲にピントが合って見えるようになります。

絞り(F値)の小さな写真は被写体を目立たせる効果があります。
絞り(F値)の大きな写真は景色などの広い場所を撮る際に活躍します。
被写界深度とは
ピントが合っているように見える範囲を被写界深度と呼びます。
カメラの理屈的にはピントが合う点は一カ所ですが、実際はその前後もピントが合って見える範囲があります。そのピントが合って見える範囲を「被写界深度」と呼びます。
(3)ISO感度について
デジタルカメラは絞り値やシャッタースピードを調節してカメラの中に入った光をイメージセンサー(撮像素子)で受け取り、受け取った光を電気信号に変換しています。
そのイメージセンサー(撮像素子)が受け取った光を電気信号に変換する際の感度をISO感度といいます。
ISO感度の数値を下げれば感度が下がるので暗くなり、上げれば感度が高くなるので明るくなります。
ただし、ISO感度を高くし過ぎるとノイズが増えてしまいます。
暗い場所の防犯カメラの映像やデジカメで撮影した暗い場所の写真にざらつきがあるのを見たことがあると思いますが、まさに写真がそんな風な仕上がりとなるのです。
設定をAUTOにしている場合は、カメラがISO感度を自動的に調整してくれますが、自分で調整する場合はむやみやたらに上げないことが一番です。
撮影モードと露出の関係
ここまで説明してきました(1) シャッタースピード、(2) 絞り(F値)、(3) iso感度とカメラの撮影モードとの関係を図に表すとこのようになります。
| 一般的な 撮影モード |
SS シャッタースピード |
絞り(F値) | ISO感度 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| P プログラムオート |
自動 | 自動 | 手動 or AUTO | 細かい設定をカメラに任せる |
| A(Av) 絞り優先モード |
自動 | 手動 | 手動 or AUTO | 絞り(F値)を自分で決めて 他はカメラに任せる |
| S(Tv) SS優先モード |
手動 | 自動 | 手動 or AUTO | シャッタースピードを自分で決めて 他はカメラに任せる |
| M マニュアルモード |
手動 | 手動 | 手動 or AUTO | 全て自分で決める |
適正露出とは
露出がちょうどよい状態を適正露出といいます。
デジタルカメラが機械的に丁度いい露出に調整してくれる機能を露出調整機能といいます。撮影モードまたは露出モードP(プログラムオート)、S(シャッター優先)、A(絞り優先)を使えばカメラの露出調整機能により適正露出を得ることが出来ます。
ただし、逆光をあえて撮りたかったのに、明るくなってしまうなど人間にとってちょうどいいとは限らないこともあります。
露出補正とは
適正露出が得にくい逆光や白い被写体、黒い被写体等を正しい露出で撮影するために使用する機能です。プラス側へ操作すると明るく、マイナス側へ操作すると暗くなります。逆光の場合は露出をプラスへ上げることで黒つぶれした被写体を写しやすくなます。黒い被写体はカメラが勝手に暗すぎると判断してしまい、黒を黒として写せない場合があり、その場合は露出をマイナスにして調整します。逆に白い被写体はカメラが明るすぎと判断してしまい暗く写ることがあるので露出をプラスにします。
露出の単位はEV、または段という単位で呼ばれ、-0.3EV(0.3段)0.5EV(0.5段) 1.0EV(1段)と示します。
-1EVなら、カメラが決めた適正露出より1段暗いという意味合いとなります。
トンネルの向こうがしっかりと見えるように露出補正をマイナス側へ操作しました。
トンネルの向こうがメインであるなら左が適正露出ですが、トンネルの内部がメインならば右が適正露出ともいえます。
実践して写真を撮ってみよう
それでも適正露出にならず迷ってしまうこともあると思います。
そういう時のために有名な【プロの秘伝レシピ】をご紹介します。
ここでは細かな説明を省きますが、簡単に言えば晴れた日は 絞りF16
を基準にシャッタースピードとISO感度を”逆数の関係”(例えばISO感度100の場合はシャッタースピードを1/100にする)にするというルールです。
サニー16ルールにのっとれば、あくまで目安となりますが屋外では適正露出が得られるといわれているテクニックです。
| 一般的な 撮影モード |
SS シャッタースピード |
絞り(F値) | iso感度 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| サニー16 | 1/200※ | F16 | 200 | 天気に応じて調整すれば尚良し♪ |
※シャッタースピードは1/200秒がない場合は1/250秒など近い数値を選びます。
晴れの日以外の場合については、絞り(F値)を小さくし、露出を上げていきます。
例えば、曇りの日はF8、暗めの曇りの日はさらに小さくしF5.6、といったように調整します。
終わりに
色々ご説明してきましたが、一番は撮りたいタイミングを逃さないことだと思います。
これは私の尊敬するプロカメラマンがインタビューで発言していた事なのですが、当たり前のようで無駄なこだわりが多く、出来ていなかったと反省させられました。
昔のフィルムの世界では1度シャッターを切ってしまえば、ネガフィルムが無駄になってしまいます。
しかし、デジタルカメラの時代になってからは、シャッターを切ってもフィルムが無駄になることはなく、暗い写真も、ピントが合っていない写真も、多少であればデジタルで修正ができます。
上手に撮るのももちろんですが、ああだこうだと考えているうちに撮りたいものを逃してしまうよりは、まずはシャッターを切る。撮れない(=写真が残らない)より、ヘタクソでも撮れた(=写真が残る)方がカメラが上手くなる道へ一歩進んでいると思うのです。
今回紹介したのはカメラの情報の膨大な中の一部。
失敗を恐れず、たくさんカメラに触れてみてください♪
写真印刷におすすめな用紙はこちら!
-
大判ポスター出力/写真光沢紙
1,160円(税込)~
表面に光沢のある紙で、写真のような仕上がりになります!
-
大判ポスター出力/写真半光沢紙
1,160円(税込)~
通常の写真光沢紙に比べてややツヤが抑えられた光沢用紙です。
-
大判ポスター出力/ハイグレード光沢紙
2,550円(税込)~
印画紙ベースの厚手写真用紙で写真光沢紙よりも、色の再現性に優れています。
※2017年12月商品改訂により旧ハイグレード光沢紙はハイグレード半光沢紙になりました。 -
大判ポスター出力/ハイグレード半光沢紙
2,550円(税込)~
印画紙ベースの厚手写真用紙で光沢微粒面になります。